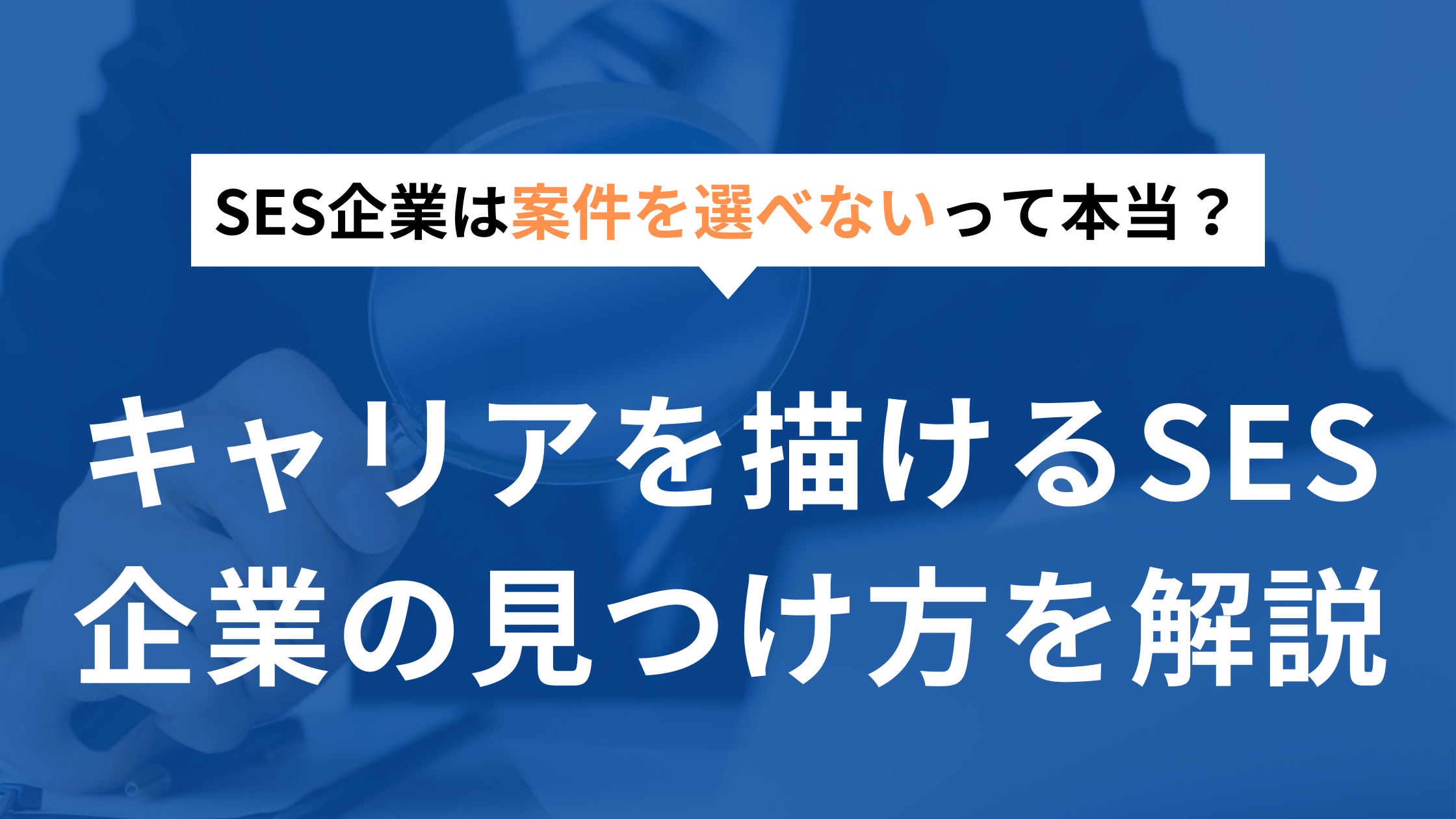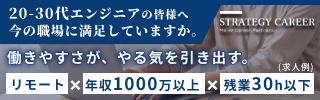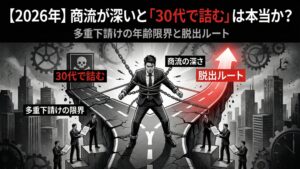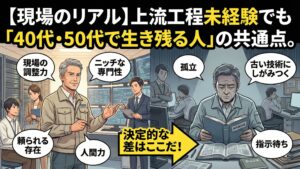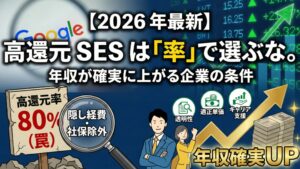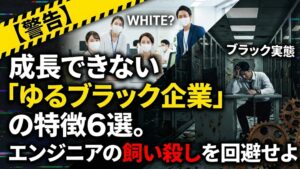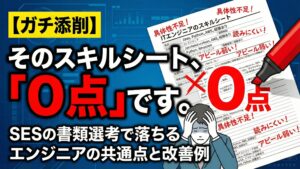「SESは案件を選べないって本当?」「キャリアが描けないまま使い捨てにされるのでは?」そんな不安を抱えるエンジニアは少なくありません。確かに案件選定の自由度はSES企業ごとに大きな差があります。本記事では、SESにおける案件選定の実態とその重要性を解説しつつ、自分のキャリアを主体的に築けるSES企業を見つけるための視点と具体策をご紹介します。
SESとは
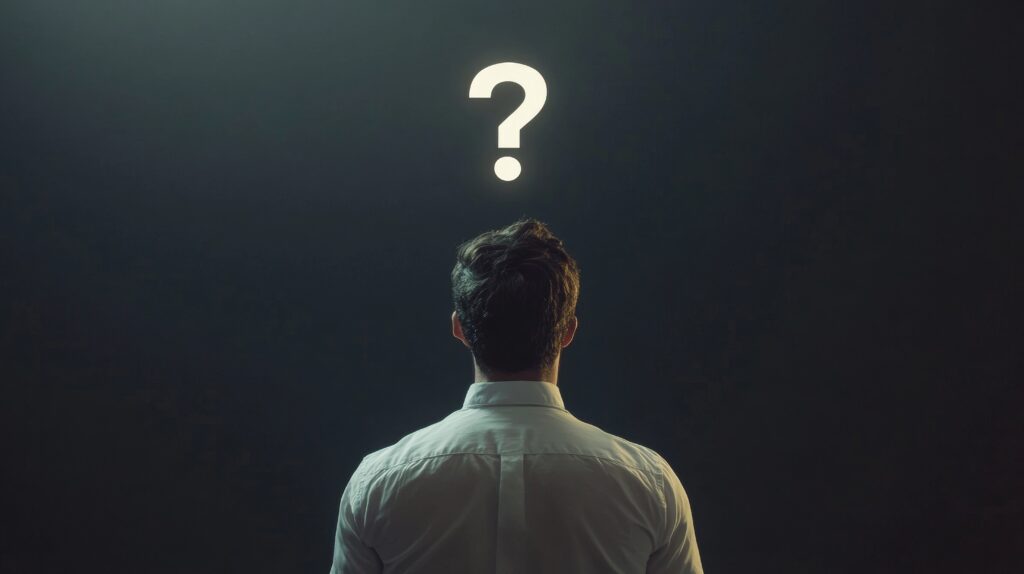
SES(システムエンジニアリングサービス)とは、自社のエンジニアがクライアント先に常駐し、業務支援を行う契約形態です。成果物ではなく労働時間に対して報酬が支払われる点が特徴です。エンジニアとしての所属はあくまで自社(SES企業)である一方、日々の業務は他社(常駐先)で行うという構造です。業務内容は開発から運用・保守、テスト、サポート業務まで多岐にわたります。このような働き方には、以下のようなメリットと課題があります。
案件選定の仕組み

SESにおける案件選定のプロセスは、企業によって異なりますが、一般的には以下のような流れになります。
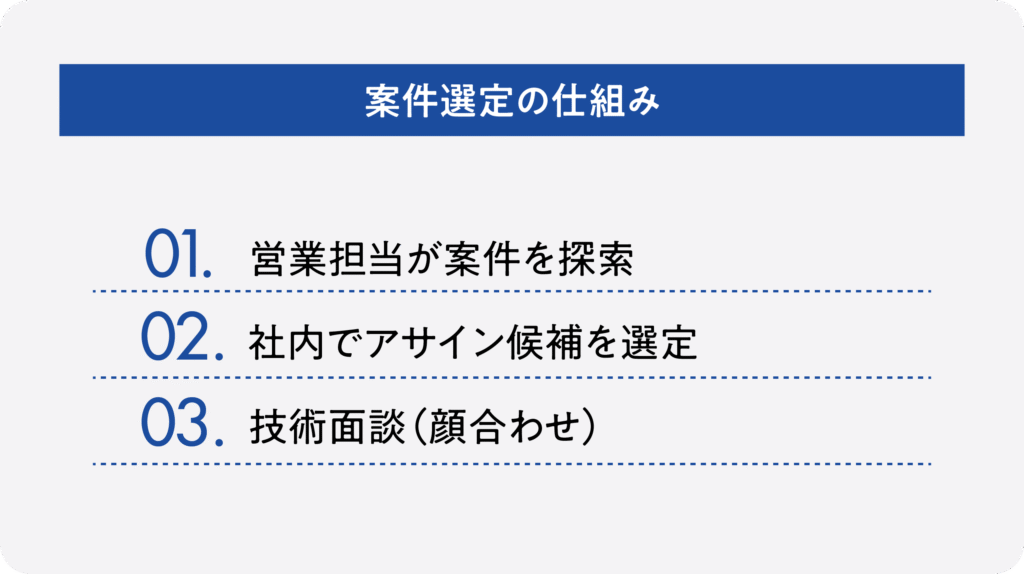
- 営業担当が案件を探索
- クライアント企業からのニーズを受け、営業が案件情報を取得します。
- 社内でアサイン候補を選定
- 社内のリソース状況やスキルマッチ度をもとに、営業や人事がアサイン候補をピックアップします。
- 技術面談(顔合わせ)
- クライアントとの面談を通じて、問題がなければ受注となりアサインが決定されます。
このプロセスの中で、「エンジニア本人の希望がどれだけ考慮されるか」は企業文化・体制により大きく異なります。本人が希望を出せず、配属先が一方的に決まってしまうSES企業では、スキルアップの機会が制限され、キャリア形成に悪影響を与えます。
案件選定の自由度はなぜキャリアに重要か?

エンジニアにとって、「どんな案件にアサインされるか」は自身のキャリア構築に直結する、極めて重要な要素です。
例えば、以下のような違いがキャリアを大きく左右します。
- インフラ系 かWeb系か
- 現場での開発経験を積めるかどうか
- モダンな技術スタックの有無
さらに、案件選定に関われる会社であれば、以下のようなキャリア形成が可能になります。
- 自分の志向に合った分野で専門性を高められる
- チームリーダー・マネジメントへの挑戦ができる
- 最新技術を学び続ける場にアクセスできる
逆に、配属が受け身であり続けると、5年後もスキルが伸びず、転職市場で「実務経験が浅い」「技術が古い」と見なされる可能性があります。
よくある“案件ガチャ”に関する先輩エンジニアの事例

ここでは、実際に「案件ガチャ」に振り回されてしまったエンジニアの事例を紹介します。
ケース1:未経験OKと聞いて入社したが、半年間「待機」扱いに(24歳・女性)
プログラミングスクール卒業後にSES企業に入社。「未経験歓迎」「研修あり」との言葉を信じて入社したが、研修らしい研修はなく、配属も決まらないまま社内待機状態に。給与も減額され、半年後には開発ではなくテスト業務にアサインされることに。
ケース2:インフラ志望だったのに、なぜかコールセンター配属に(28歳・男性)
インフラ系技術を学んできたが、営業が「人手不足で急募」との理由でコールセンター(技術サポート)業務に配属。配属後は問い合わせ対応に追われ、自分が目指していたキャリアと大きく乖離。モチベーションを失い、1年後に転職。
案件選定に関われる企業とそうでない企業の違い

SES企業において「エンジニアが案件選定に関われるかどうか」は、キャリア形成に大きな影響を与えます。ここでは、案件選定に関われる企業とそうでない企業の違いを、5つの観点から順を追って解説します。
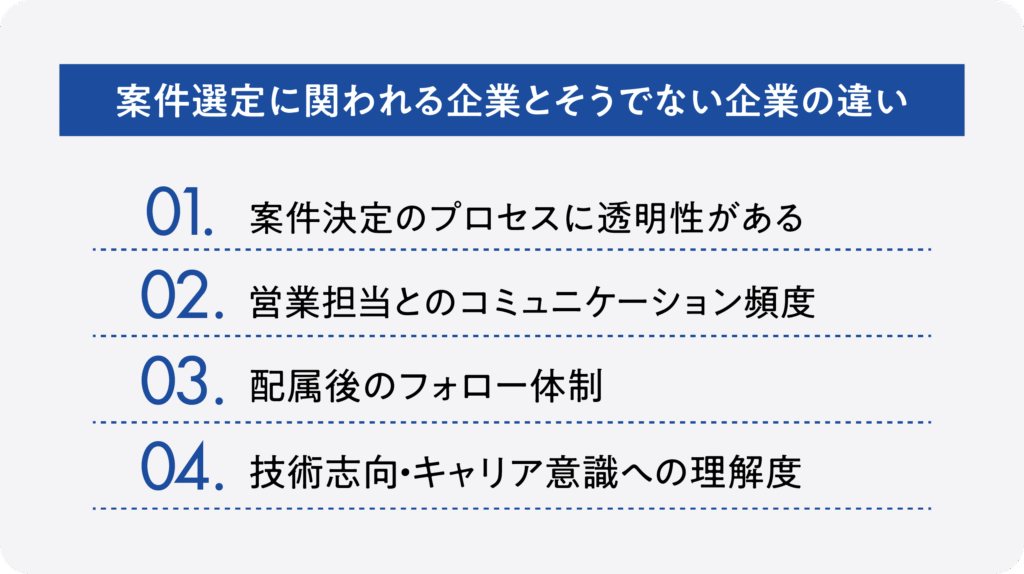
① 案件決定のプロセスに透明性がある
案件選定に関われるSES企業では、エンジニアがアサインされる前に「複数の案件候補」が提示され、技術内容・勤務地・チーム構成・期間などの詳細も共有されます。そして、「この案件とこの案件、どちらが希望に近いですか?」といった形で本人の意思確認を経て決定されるため、納得感が非常に高いです。
一方で、関われないSES企業では、本人の希望を聞かないまま「○日からこの現場に入ってください」と一方的に通知されるだけで、実質選択の余地がありません。
② 営業担当とのコミュニケーション頻度
良質なSES企業では、営業担当がエンジニアのキャリア希望やスキルを正確に把握しています。営業がクライアントとのやり取りの中で「この人にはこの案件が合いそうだ」と考え、エンジニアとも事前に相談しながらアサインを調整します。
対して、営業とエンジニアの接点がほぼなく、「人が空いているからとりあえず入れる」という運用がされている場合、希望の反映はほぼ期待できません。
③ 配属後のフォロー体制
案件選定に関われるSES企業では、配属後も月1回以上の面談を通して「この現場はどうか」「キャリアに合っているか」などを継続的に確認してくれます。場合によっては、現場変更の交渉にも動いてくれます。
一方で、配属されたら連絡が途絶える、相談しても「我慢してください」で済まされるようなSES企業では、次のアサインにも希望が反映されづらい傾向があります。
④ 技術志向・キャリア意識への理解度
案件選定に関われるSES企業は、「エンジニアがキャリアを築けるかどうか」を重視しています。そのため、スキルマップの整備やキャリアパスの設計支援、キャリア面談といった仕組みが整っています。
反対に、業務が「人月商売」であることだけを重視するSES企業では、「案件に入れる=売上が立つ」ことが最優先され、本人の成長や希望は二の次にされがちです。
エンジニアが案件を選ぶためにできる5つの工夫

エンジニア本人が「案件選定に関われる存在」になるためには、SES企業任せにせず主体的な行動も欠かせません。
案件を選べるかどうかは、エンジニア自身の行動や工夫によっても大きく左右されます。ここでは、現場エンジニアが実践して効果のあった「主体的に案件を選びやすくするための工夫」を5つ紹介します。
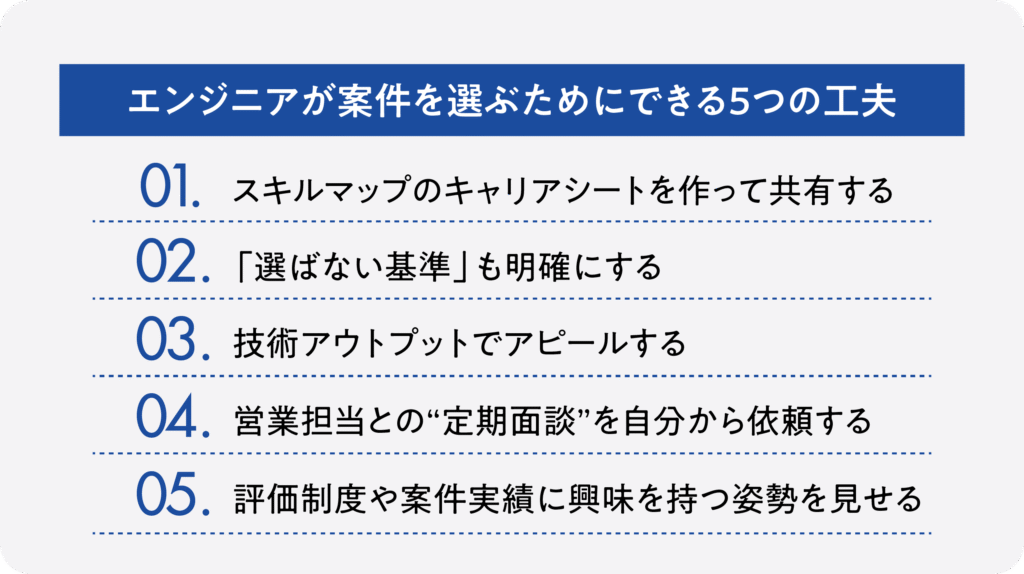
① スキルマップとキャリアシートを作って共有する
営業や上司に自分のスキルや希望を正確に伝えるために、「スキルマップ」や「キャリアシート」を自主的に作成しましょう。以下の内容を含めると効果的です。
- 使用経験のある言語・ツール・環境
- 現場で経験した業務範囲(設計・実装・テストなど)
- これから伸ばしたいスキルや興味のある分野
- 将来的に目指すロール(PM・フルスタック・スペシャリストなど)
これを営業担当に共有すれば、マッチする案件の打診がしやすくなり、希望から外れたアサインも減らせます。
② 「選ばない基準」も明確にする
何が「やりたいか」だけでなく、「やりたくないこと・避けたい業務」も明文化しましょう。例としては以下のようなものがあります。
- 運用・監視などの保守的な業務はNG
- ユーザーと接点がない非開発の業務は避けたい
- 古い技術環境(VB、COBOLなど)は希望しない
あらかじめ伝えておくことで、営業側も案件選定時にフィルタリングしやすくなります。
③ 技術アウトプットでアピールする
GitHubにコードを上げる、QiitaやZennで記事を投稿するなど、外部への発信を通じて自分のスキルと意欲を可視化すると、営業やSES企業からの評価も上がります。
技術イベントでのLT登壇や、社内勉強会の主催なども効果的です。「開発に本気で取り組んでいる人」という印象を与えられれば、希望の案件に推薦されやすくなります。
④ 営業担当との“定期面談”を自分から依頼する
待っていても希望通りの案件を提案してくれる営業担当がいれば理想ですが、待っているだけでは案件の希望は通りません。むしろ自分から月1の面談を依頼し、希望やスキル変化を伝えることで、意思表示の習慣を持ちましょう。
会話の中では以下のトピックを話すと効果的です:
- 現在のの現場での困りごと
- どんな技術に挑戦したいか
- 近い将来チャレンジしたい役割(リーダー経験、上流工程など)
⑤ 評価制度や案件実績に興味を持つ姿勢を見せる
「どんな案件が他のエンジニアに紹介されているか?」「自社の評価制度はどうなっているか?」に関心を持ち、調べたり質問したりする姿勢も重要です。営業や上司からも、「この人は本気でキャリアを考えている」という印象を持ってもらえます。
案件が選べるSES企業の見極め方

最後に、そもそも「案件を選びやすいSES企業」かどうかを見抜くには、以下のような視点が必要です。ここでは求人情報だけでなく、面談時に聞くべき質問例まで含めて詳しく解説します。
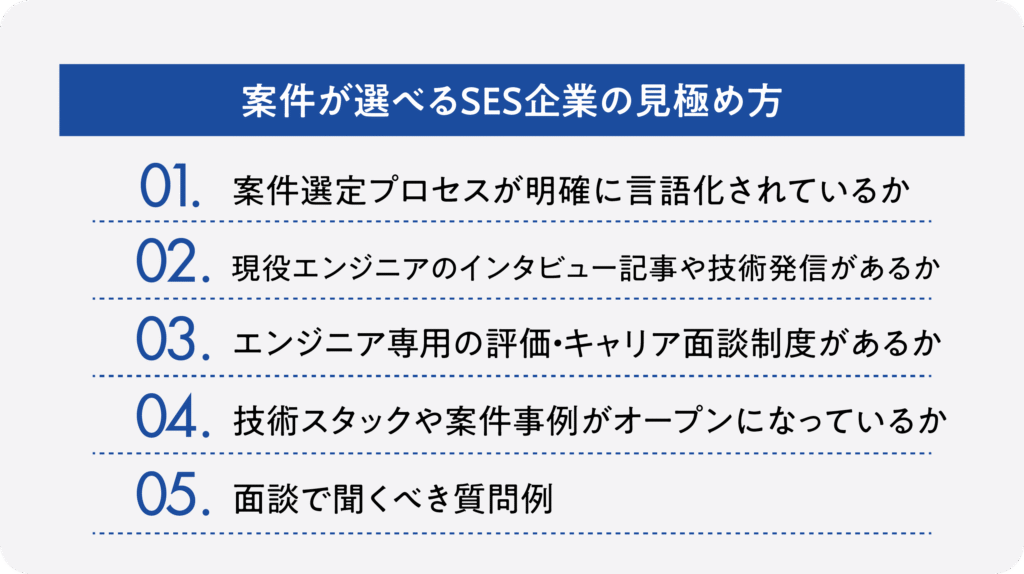
① 案件選定プロセスが明確に言語化されているか
企業説明や面談で「どうやって案件が決まるか」という質問をしたときに、次のような回答があれば安心です。
- 「案件候補を3つ程度提示し、本人と相談して決定します」
- 「キャリアマップをもとに営業と1on1で調整します」
- 「技術志向に応じた案件選定会議を月1回実施しています」
逆に「営業が決めてます」「アサインできるところに入ってもらいます」といった回答しか得られない場合は要注意です。
② 現役エンジニアのインタビュー記事や技術発信があるか
企業の公式ブログやYouTube、Wantedlyなどに「現場エンジニアの声」があるかは重要な判断軸です。特に以下のような内容が発信されていれば、案件選定の自由度や開発志向が高いSES企業と考えられます。
- 「どういう基準で案件を選んでいるか」
- 「キャリアの節目で異動を相談できた話」
- 「営業とどんな関係性で動いているか」
③ エンジニア専用の評価・キャリア面談制度があるか
毎月もしくは隔月でキャリア面談を行う文化が根づいていれば、希望の案件に関われる可能性が高くなります。また、「目標に対してどう案件を組み合わせるか」といった会話が日常的に行われているSES企業は、成長を本気で支援する意識がある証拠です。
④ 技術スタックや案件事例がオープンになっているか
企業HPや採用資料、求人票に「使用言語」「開発手法(アジャイルなど)」「参画工程」などが書かれているかは見極めポイントです。逆に「IT業界全般」「幅広く案件多数」といった曖昧な表現ばかりの場合は要警戒です。
⑤ 面談で聞くべき質問例
最後に、案件選定の自由度を見極めるための質問例をご紹介します。
- 案件はどうやって決まるのですか?何案くらい提示されますか?
- 案件選定にあたってエンジニアの希望はどれくらい考慮されますか?
- キャリアパスの中で開発・マネジメントなどの分岐はどう描かれていますか?
- 案件が合わなかった場合、変更の相談はできますか?
これらに対して納得感のある説明ができるSES企業は、エンジニアにとっての「選択権」をきちんと保証しているSES企業と判断できます。
まとめ

SES企業=案件を選べないというイメージは一部正しいですが、すべてのSES企業に当てはまるわけではありません。むしろ、キャリア志向の高いエンジニアが主体的に動くことで、自分の将来を見据えた案件に関われるSES企業も多数存在します。
この記事で紹介したように、案件選定に関われるかどうかは、企業体制・文化・そしてエンジニア自身の姿勢によって大きく変わります。「自分のキャリアは自分で作る」という意識を持ち、SES企業選びと日々の行動を見直していくことが、SES業界で後悔しない働き方を実現する鍵となります。